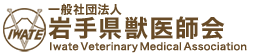よくある質問
動物のしつけ
- 犬の「しつけ」はどうしたらいいのでしょうか?
-
「しつけ」は、ワンちゃんと共同生活をするために「とても大切なもの」です。そのためにも飼い主は、立派な尊敬できる好いリーダーになることです。
犬は「群れ=集団=家族」を作って生活する動物です。家族の中における自分を「人」と思っているのではなく、家族を一つの「群れ」と認識して暮らしています。犬の「幸せ」は2つあり、ひとつは「群れの中でリーダーになること」、もう一つは「いいリーダーに巡り会うこと」です。家庭の中で飼うときは、言うまでもなく人がリーダーにならないといけません。無理矢理いやなことをさせるのは良いリーダーではありません。力ずくで言うことを聞かせるのではなく、犬が喜んで人に従っているようにしなければなりません。
また、犬が「自分が偉い」と勘違いをしないように、普段から「ごはんは家族の最後にする、目の前で家族げんかをしない、散歩は人間がリードする、肩に抱いたり犬の目線の方を高くさせない」などに気をつける必要があります。
また何かを与えるときには、まず人間が命令をし、それに従ったご褒美としてものをあげるようにしましょう。犬が要求したり、主導権を取っているときに報酬を与えるのは、犬が勘違いして「アルファ・シンドローム」などの問題行動の原因になります。
- おすわり・ふせ・まて・おいでなどのしつけはどうすればできるの?
-
幼いうちは完全にするのは無理ですが、少しずつできることを教えていきましょう。ポイントは、無理強いさせない・成功したらその場でオーバーなくらい思い切りほめるということです。自然に犬がそういうポーズをとるようにし、したら褒美をあげるようにします。
例えば、おすわりも無理に尻を押し下げるのでなく、おやつを目の上に持っていって、自然と腰が下がったらすかさず「すわれ」と声をかけて、それからおやつをあげます。そうすると、座った行動と号令と、ご褒美が結びついて記憶されます。
次第に喜んで号令に反応するようになります(陽性強化)。無理にさせてそれが支配性につながるのではなく、よろこんで命令に従うことで人間を良いリーダーと認識していくのだと覚えておいてください。
- 「噛み癖」や「飛びつき癖」をなおしたいんですが?
-
子犬には、ものを噛んだり、じゃれたりする本能があります。特に、生後4~6ヶ月は乳歯から永久歯への抜け替わりの時期なのでとりわけ歯がむずむずします。それはストレスとなり発散させてやらないといけないのですが、人にとっても犬にとっても「危険のない方法」で行うことが必要です。いわゆる「じゃれ噛み」の時に手を噛ませて遊んだり、声を上げてかまったりすると、人を噛むと楽しいと学習して、後に「問題行動」として困ったことになってしまいます。
人にとって好ましくない行動をしているときは、まず褒美を与えないということを徹底すること。そういう行動をし始めた時には、声もかけずにその場を立ち去るか、行動をとれない状態にするか(飛びついてきたときに軽く膝蹴りなど)、「だめ!」とひと言いって叱りつけるかです。
叩いたりすると、よけい興奮したりすることもあるのでおすすめできません。その代わりに噛んでも差し支えない、犬にとって好ましい「おもちゃ」を与えましょう。基準は、犬にも無害で単純構造のわかりやすい物で、コング(ゴムのおもちゃ)などがおすすめです。古靴下や古靴・古スリッパなどの生活用品は、犬にとって新しいものとの区別が付かないので止めて下さい。
靴などを噛んでいるときにそれをとろうとすると、大切なものを横取りされると考えて奪われまいとしたり、噛みついてきたりすることもあるので気をつけてください。目を離した隙に片付けた方がいいでしょう。
主導権は人間が持つことが大切です。犬は群れの中での順位をいつも考えている動物ですが、リーダーになるのは人間でなくてはいけません。鳴いたからかまってやる・吠えたからごはんをやる…などとしていたのではどちらが主人か分かりません。犬がご褒美をもらえるときは、犬が望んだからもらえるのではなく、人に従ったときだけもらえるという習慣でしつけの基本を統一しましょう。
犬が何かを要求したときにはいったんその要求は無視し、間をおいてからお座り・お手などをさせ、それができたらはじめて褒美を与えるようにしてください。飼い主が食事を与えていたとしても、「犬が命令して人が給餌している」という形であれば、犬は飼い主のことを「召し使い」くらいにしか思っていないこともあります。
- 隣家から犬の鳴き声がうるさいと苦情を言われてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
-
犬が鳴いている時に大きな声で怒ることは逆効果になることがあります。なぜ鳴いているのか、その理由や原因を観察することが必要です。
早く散歩に行きたい、早くごはんが食べたいなど要求吠えの場合は、目を合わせたり声をかけたりせずに無視します。鳴き続けている場合は気づかれないように、大きな音の出るもの(空き缶に小石を入れたもの等)を犬にあたらないように投げます。驚いて鳴くのをやめた時に十分ほめてください。
縄張意識や警戒心から他人に対して鳴き続ける場合は「オスワリ」させて落ち着かせます。「静かに」、「ヤメ」などの合図で鳴きやんだ時に十分ほめてください。人通りの多い場合、犬が安心できる場所に飼育場所を変えることも必要です。すぐに効果が出るものではありません。飼い主さんをリーダーとして認識させ、どのような状況でも合図に従うよう繰り返し練習することが重要です。